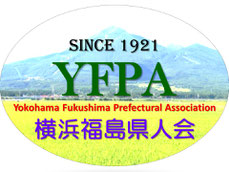人を運ぶだけでなく、その土地の産業を支える役目も果たしてきた鉄道。
時代が移り変わり、戦後およそ400の路線が廃線となりましたが、今もなおその名残をとどめる場所も多く、
廃線をめぐる旅も人気を集めています。
福島県内で廃線となった4路線を紹介します。
日中線(NHK アーカイブスより)
日中(にっちゅう)線は、福島県喜多方市の喜多方駅から熱塩(あつしお)駅までを結んでいた、全長11.6kmの路線。1980年の国鉄再建法の施行により、1984年に全線廃止となりました。末期は、朝1往復、夕方から夜間にかけて2往復の1日3往復のみで、日中は「走りま」線と言われました(笑)。SL廃止後はディーゼル機関車牽引となり、ディーゼルカーが用いられることはなく、最後まで客車列車で運行されました。
川俣線(NHK アーカイブスより)
川俣(かわまた)線は、福島県福島市の松川駅と伊達(だて)郡川俣町の岩代川俣駅を結ぶ全長12.2kmの国鉄路線で、1972年に廃線となりました。さらに太平洋側の常磐線浪江駅まで延伸する計画は実現せず、1926年の開業以降、川俣特産の羽二重(はぶたえ=高級絹織物の一種)の出荷などに利用されました。太平洋戦争中の1943年には「不要不急線」として営業休止。線路はほかの路線に転用されました。1946年に運行が再開され、小さなC12形SLが客車と貨車を一緒に引く「混合列車」が、ファンの人気を集めていました。廃線後、川俣町内に保存されていたC12形66号機が復元。1994年から栃木県の真岡鐡道で、「SLもおか」として活躍を続けています。映像は、1972年放送「福島ニュース」より。
江名鉄道(NHK アーカイブスより)
江名(えな)鉄道は福島県小名浜の栄町駅と江名駅を結ぶ全長4.8kmの路線で、1967年に廃線になりました。小名浜臨海鉄道の延長線の形で開業し、車両はすべて小名浜臨海鉄道のもので賄われた。当初から採算がとれず、13年ほどで廃止になりました。映像は、1966年放送「NHKニュース」より。
磐梯急行電鉄(沼尻鉄道)(NHK アーカイブスより)
磐梯(ばんだい)急行電鉄(沼尻鉄道))は、かつて福島県耶麻郡猪苗代町の川桁駅と沼尻駅とを結ぶ全長15.6kmの路線で、1969年に廃線になりました。硫黄鉱石を運ぶために建設されましたが、鉱山の閉山後は観光輸送に活路を見いだし、沿線のリゾート開発を目指すため、「急行電鉄」と名乗りました。しかし、電化されることもなく、急行列車が運転されることもなく、小型のディーゼル機関車が客車を牽引してゆっくりと走っていました。歌謡曲「高原列車は行く」の歌詞は、この鉄道の車窓風景を詠んだものと言われています。映像は、。1968年放送「話題を追って」より
福島交通 飯坂東線(NHK アーカイブスより)
福島交通 飯坂東(いいざかとう)線は、かつて福島県福島市及び伊達町・保原町・梁川町(いずれも現在の伊達市)などにおいて運行されていた福島交通の軌道線(路面電車)で、1971年(昭和46年)4月12日に全線廃止されました。細身の路面電車が舗装されていない郊外の砂利道の片隅を走る姿が特徴でした。また貨物輸送も行われ、電動貨車が小さな貨車を3両ほど牽引して、路面を走っていました。映像は、2006年放送「NHKニュース」より。